資産運用
もしもの時の遺族年金額を知ろう - 退職・年金ナビ
投稿日:2013/06/27
最終更新日:2022/08/01
本コンテンツは当サイト編集部が独自に制作しております。各広告主様やアフィリエイトサービスプロバイダ様から商品案内や広告出稿をいただくこともありますが、各事業者様がコンテンツ内容等の決定に関与することはございません。本サイトは広告およびアフィリエイトサービスにより収益を得ています。コンテンツ内で紹介した商品が成約されると、売上の一部が当サイトに還元される場合があります。
目次 [ ]
退職・年金ナビ [ 保険の買い方選び方 ]
【第4回】
もしもの時の遺族年金額を知ろう
- もしもの時の必要死亡保障額を正確に算出するためには、遺族年金の知識が必須です。どんな状態になったら国からどんな年金がいくらくらい支給されるのかをあらかじめ知っておきましょう。
-
遺族年金とは
- 年金に加入中の人や加入していた人などが死亡した時に、遺族に支給されるのが遺族年金。自営業等の人(国民年金第1号被保険者)が亡くなった場合は国民年金から、会社員や公務員等(第2号被保険者)の場合は、要件があえば厚生年金や共済年金からと国民年金からの両制度から受給することができます。それでは、夫が死亡した場合の妻についてどのような遺族年金が支給されるのか具体的にみてみましょう。
-
18歳未満の子がいる妻に支払われる遺族基礎年金
- 18歳未満の子(高校卒業の年度まで)がいる妻には、国民年金から遺族基礎年金が支給され、子の加算もあります。ただし、子どもが全員対象からはずれると遺族基礎年金が打ち切られるので、注意が必要です。
-
夫が会社員や公務員なら遺族厚生年金と遺族共済年金も
- 夫が会社員や公務員の場合は、遺族厚生年金と遺族共済年金も支給されます。年金額は、加入実績に応じた老齢厚生年金(共済年金)の4分の3で、妻が生きている限り支払われます。また、子が高校を卒業して遺族基礎年金がストップしても、代わりに中高齢寡婦加算が、妻の老齢基礎年金が支給される64歳まで支給されます。
-
子がいない妻に支払われる遺族年金
- 子がいない妻には、遺族基礎年金は支給されません。また、夫の死亡当時30歳未満の場合は、5年で遺族厚生年金の権利がなくなり、さらに40歳以上64歳までの妻に支給される中高齢寡婦加算が死亡当時40歳未満の妻には支給されません。このように見てくると、若くて子がない妻には、十分な遺族年金がもらえないと言えるかもしれません。
-

-
ねんきん定期便で遺族厚生年金の額をチェック
- 厚生年金や共済年金は基礎年金のように一律の年金額ではないため、自分で計算することが難しいのですが、遺族厚生年金については、日本年金機構から毎年誕生月に送付される「ねんきん定期便」を活用することで、概算額を把握することが可能になりました。
- 遺族厚生年金は夫の実際の加入期間と報酬に応じて支給されますが、厚生年金加入中に亡くなり加入期間が短い場合には、最低300月(25年)加入したとみなして計算します。そのため、入社してすぐに亡くなっても、一定額以上の年金が保障されているのです。それでは、下記の「ねんきん定期便」から、夫が亡くなった場合の遺族厚生年金額を試算てみましょう。まずは「これまでの加入実績に応じた老齢厚生年金額」をチェック。この金額は厚生年金の加入期間が150月の金額なので、300月として計算し直さなければなりません。
- そこで1カ月分がいくらになるかを計算してそれに300月を掛けるとおおよその老齢厚生年金額が出ます。それに4分の3を掛けることにより遺族厚生年金額がわかるというわけです。
- もちろん300月以上加入期間のある方は、加入実績に応じた老齢厚生年金額に4分の3を掛けるだけで求めることができます。
-

- また、50歳以上の方には、「ねんきん定期便」に老齢厚生年金の見込額が記載されていますので、これを3/4することにより遺族厚生年金が簡単に算出できます。なお、この見込額は今の報酬で60歳まで働いたと仮定した金額ですので、少し控え目な数字を用いるとよいでしょう。
- 夫に不測の事態が起こった場合、遺族年金は大きな助けとなります。ただし、漠然と考えていたのでは、いざという時に「年金だけではとうてい生活できない」と後悔することになるかもしれません。前もって遺族基礎年金、遺族厚生年金がいくらもらえるのかを知っておくことは、必要死亡保障額の算出をより確かなものにし、安心して生活をしていくために必要な一つの知恵だと言えるでしょう。
-

- 執筆:ファイナンシャル・プランナー 菅田 芳恵
所属:プラチナ・コンシェルジュ
掲載日:2011年月03月08日
最新ネット証券比較ランキング
口座開設されてない初心者の方に向けた、ネット証券が比較できる最新ランキングTOP10はこちらです。口座開設手続きはネット上で完結できます。口座開設キャンペーンもご紹介してます。是非この機会に、ネット証券の口座開設を行ってみましょう。

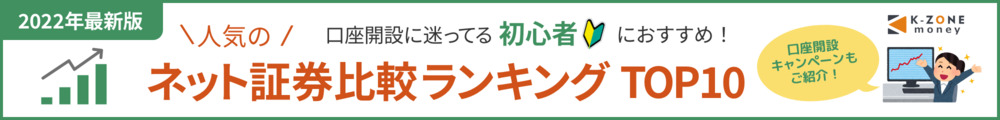
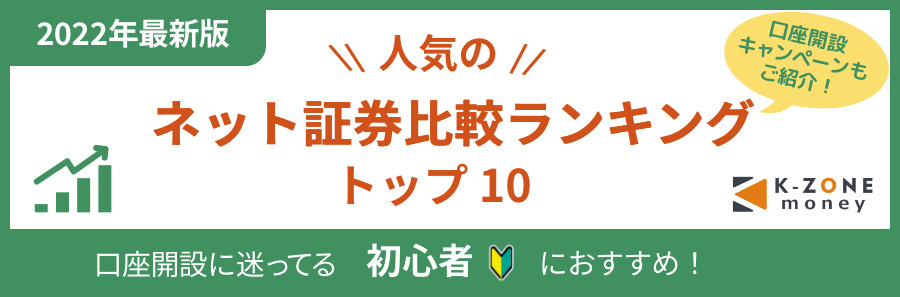



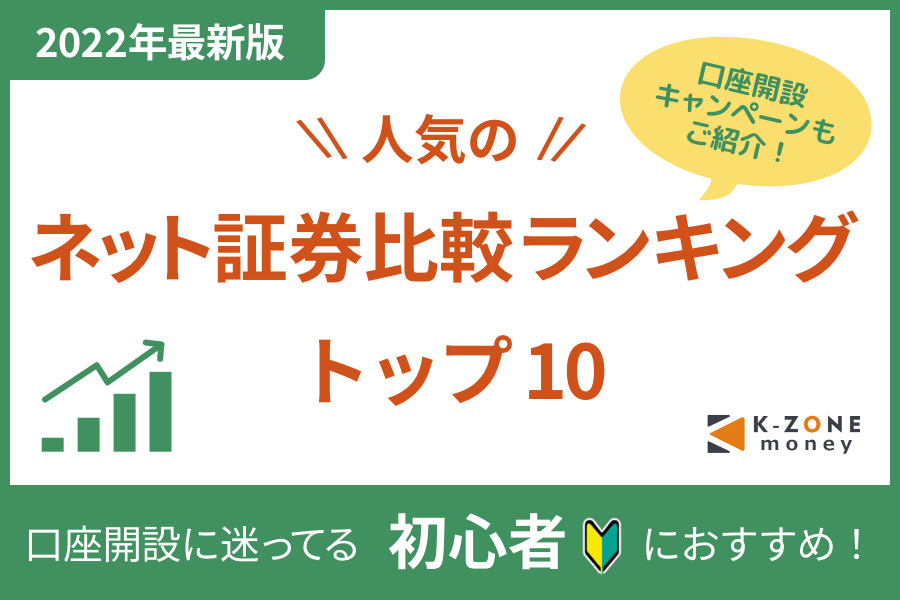


.png)
.png)


.png)
.png)
.png)



