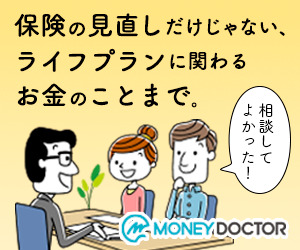赤ちゃんを迎えるにあたって、何かと必要なお金はかさみます。産休に入り収入が得られなければと、産後の生活費などの家計のことで不安に思われる妊婦さんもいるかと思います。
出産のために会社を休み、給与を受け取れない場合は、健康保険から出産手当金が支給されます。ただし、出産手当金は自動的に支払われるわけではなく、自分自身で申請しなければなりません。
出産はただでさえ負担が大きいものです。したがって、事前にお金の制度や利用・手続きなどに関する情報を得て理解しておくことは、ストレスを軽減する上で有意義だと言えます。本記事では出産手当金の計算方法や、申請方法について詳しく解説します。
出産手当金とは?
出産手当金とは、会社などで仕事をしている健康保険加入者である女性が出産で休職する際に、健康保険から支払われる手当金のことです。出産で仕事を休職し、収入が大幅に減るため、出産するまでの期間や出産後の生活、育児をを支えるためのお金が支給される制度となっています。支給される金額は出産する人の給与所得に応じて変わります。事前にどれだけの出産手当金がもらえるのか、受け取れる時期や受給要件・条件、計算方法や申請の仕方を確認しておきましょう。
| 【関連記事】妊娠・出産での保険加入は必要?妊娠・出産時でのかしこいの保険選び |
出産手当金とはどんな制度?
労働基準法第65条により、女性は産前産後休業(産前6週間・産後8週間)を取得できますが、会社や事業者にその女性従業員が休んでいる間における給与の支払い義務はありません。しかし、妊婦さんになるからには、職場復帰まで育休中の生活費や子どもが産まれた後の子育てに関する養育費などがかかるため、働く女性としては不安に思います。
会社から給与がでない場合、健康保険の給付として「出産手当金」が支給されます。支給対象は被保険者である労働者自身で、給付期間は産前産後休暇中です。給付額はそれまでの給与と産休期間によって決定されます。
また、出産に関して支給されるものに「出産育児一時金」や「育児休業給付金」もあり、名称が似通っているため混同しがちです。それぞれの対象者、給付額などについて仕組みの違いを見ていきましょう。
出産育児一時金との違いは?
制度の違いとして、出産手当金が産休中、給与を受け取れない間の生活保障であるのに対し、出産育児一時金は出産にかかる費用の負担軽減を目的にしたものです。出産は通常の疾病とは異なるため、加入者であっても健康保険を使うことはできません。
つまり、本来であれば通常の疾病以外は全額自己負担となりますが、出産費用については健康保険から金額補助が出ます。この助成金が出産育児一時金です。
また、出産手当金と違い、自分(出産する女性自身)が健康保険に加入している場合だけでなく、配偶者の健康保険被扶養者となっている方も含めたすべての妊婦さんが対象者です。そして、出産手当金は産前産後休暇の期間と被保険者の給与によって支給額が変動しますが、出産育児一時金の支給額は2023年4月より基本的に赤ちゃん1人当たり50万円へと増額しました。該当する場合はしっかり支給申請しましょう。
加えて、利用する場合の申請先の違いも挙げられます。両者とも基本的には、妊婦さん本人が勤務先の健康保険組合、協会けんぽ、共済組合などに申請します。しかし大きな違いとして、出産育児一時金では、被保険者の扶養家族(扶養内の配偶者など)が出産する場合、被保険者が家族出産育児一時金としてお金を受け取れるように申請することができます。
なお、2022年1月より、産科医療補償制度の掛け金が1.6万円から1.2万円に引き下げられ、出産育児一時金の支給額については、2023年4月より50万円となりました。
子育てに関するお金についての制度は、政府や全国健康保険協会の施策として様々な情報が発表されています。こまめに確認しておくとよいでしょう。出産育児一時金の詳細に関しては以下のサイトも参考にしてください。
厚生労働省「出産育児一時金の支給額・支払方法について」
| 出産手当金 | 出産育児一時金 | |
| 出産手当金 | 産休中の生活保障 | 出産にかかる費用の負担軽減 |
| 申請先 | 本人が加入している勤め先の健康保険組合、協会けんぽなど | 本人が加入している勤め先の健康保険組合、協会けんぽなどや、国民健康保険。扶養家族として夫の勤務先の健康保険に加入している人は、「家族出生育児一時金」として申請も可能 |
| 給付金額 | 妊婦本人の給与額と実際の出産日による | 胎児一人につき42万円 |
育児休業給付金との違い
育児休業給付金は育児休業を支援するための制度です。出産手当金、出産育児一時金との違いは給付対象者です。休業中に収入がなくなってしまうのは問題です。この状態をサポートするため、仕事への復帰を前提に、育児休業へのハードルを下げる目的で国が給付しています。育児休業給付金は父親・母親共に対象になっています。また、給与と育休期間によって実際に受け取れる金額が変動します。
加えて、2022年10月より、産後パパ育休(出生時育児休業)の制度が施行されました。産後パパ育休(出生時育児休業)は、通常の育児休業とは別の制度になります。産後パパ育休は、出生後8週間の間に4週間まで取得することができます。ただし、育児休業開始の2週間前までに申し出が必要です。また、分割取得も可能となっております。
詳しくは、以下厚生労働省のサイトも参考にしてみてください。
厚生労働省「産後パパ育休について」


出産手当金の対象
出産手当金の対象は条件があり、資格を得るには以下3つの条件をすべて満たしている必要があります。
出産手当金の対象条件
-
健康保険の被保険者である
-
出産のため休業している
-
妊娠4ヶ月(85日)以降の出産である
これらの受給要件にかかわる条件について詳しく見ていきましょう。
健康保険の被保険者であること
申請者本人(妊婦本人)が、勤務先の健康保険組合・協会けんぽ・共済組合などに加入している会社員や公務員でなくてはなりません。正社員でなくても契約社員やパート、アルバイトなども、健康保険に加入していれば給付対象です。
出産のため休業(産休)していること
給付を受けるには産前産後休業中で給与を受け取っていないことが条件です。産前休業で、給与が支給されていないか確認しましょう。産休中に給与の支払いがあっても、その給与の日額が出産手当金の日額より少ない場合は、その差額が受給額として給付されます。
妊娠4ヶ月(85日)以降の出産であること
健康保険において「出産」は妊娠85日(4ヶ月)以降の分娩を指します。そして、この条件は死産、早産、流産、人工妊娠中絶となった場合も含まれます。一方、85日未満での早産や死産などの場合は、出産手当金は給付されません。
\ お金・保険のことならマネードクターへ /
手当の対象とならない場合
上記の要件に一つでも当てはまらない場合は手当の対象とならないことがあるので、注意しましょう。また、以下のケースは出産手当金給付の対象外です。
国民健康保険加入のフリーランスや自営業である場合
出産手当金は社会保険の制度であるため、妊婦本人が勤務先の健康保険に加入している場合に受け取ることができます。そのため、国民健康保険に加入しているフリーランス、自営業者といった国民年金第1号被保険者の人は申請できません。ただし、会社で加入している健康保険が国民健康保険組合である場合、給付される場合があります。一方、出産育児一時金は社会保険・国民保健関係なく給付されます。
また、フリーランス、自営業者の人であっても、出産予定日または出産日の前月から4ヵ月の間、国民年金保険料の支払いは免除されます(多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日の月の3ヵ月前から6ヵ月間)。
扶養家族である場合
出産手当金を受け取ることができるのは被保険者本人のみです。そのため、出産する女性が夫や家族の扶養に入っている場合、出産手当金を受け取ることができません。ただし、前項の場合と同様、出産育児一時金の給付対象にはなります。
したがって、正社員でないパート・アルバイトでも、夫の扶養に入っている場合には、被保険者ではなく被扶養者であるため、出産手当金の受給資格はありません。
産休中に一定以上の給与を受け取っている場合
出産手当金は産休中、給与をもらえない労働者の生活保障を目的にしています。そのため、その期間に会社から出産手当金以上の基本給などの給与が支払われている場合は、出産手当金を受け取ることができません。産休中に有給を取得している場合も同様です。ただし前述のとおり、給与の日額が出産手当金の日額より少ない場合は、その差額を受け取ることができます。
健康保険の任意継続被保険者である場合
健康保険には、任意継続という制度があり、退職などの理由で勤務先の健康保険を抜けた場合、個人の希望により健康保険に継続加入して「任意継続被保険者」になることができます。しかし、原則として任意継続被保険者の場合は出産手当金を受け取ることができません。ただし、例外の参考として健保法第104条による継続給付の要件を満たしている場合は除かれます。
<健保法第104条>
被保険者の資格を喪失した日(任意継続被保険者の資格を喪失した者にあっては、その資格を取得した日)の前日まで引き続き一年以上被保険者(任意継続被保険者または共済組合の組合員である被保険者を除く。)であった者(第106条において「一年以上被保険者であった者」という。)であって、その資格を喪失した際に傷病手当金、または出産手当金の支給を受けているものは、被保険者として受けることができるはずであった期間、継続して同一の保険者からその給付を受けることができる。
このように、出産手当金の支給には、当該のような例外のケースもあるため、自分が受給要件を満たしているか、手続きを行う前に確認しましょう。
出産手当金が給付される期間
出産手当金の支給対象期間は原則出産予定日の42日前(出産日は産前に含む)から出産日後56日目までの98日間です。つまり、給与の支払いがなかった産前産後休業(いわゆる産休)中が出産手当金の支給日の対象です。
実際の出産が予定日より遅い場合、遅れた日数分も申請できます。予定日より早い場合、出産日から遡って42日間は条件を満たせば出産手当金を受け取ることができます。例えば、予定日42日以前から産休をとったが予定日より1週間早く出産した場合は、給付を受けることのできる期間は予定日ではなく「出産日から」遡って42日以前の「給与を受けていなかった」期間です。予定日と出産日の差となる産休前7日間のうち、給与を受けていた期間は出産手当金が給付されません。


給付における注意点
出産手当金の給付を正しく受け取るには、いくつかの注意点があるため知っておきましょう。
まず、出産日は出産前の期間に含まれます。次に、多胎妊娠の場合(双子、三つ子など)は産前98日、産後56日が出産手当金の対象期間です。支給日数が少々変わります。そして、給付対象期間は実際に会社を休み、給与を受け取っていないことが前提です。
そのため、給与を受け取る有給休暇は原則として支給の対象外です。(賞与の受給は減額の対象にならない)おすすめとして、もし産休にプラスして有給休暇をとる場合は、出産対象期間外で申請したほうがいいでしょう。
このように、出産手当金の給付と両立するためには、有給休暇をスムーズに調整することが肝心です。
退職した場合には適用される?
一般的には退職すると、健康保険の被保険者資格を失います。そのため、退職すると出産手当金の支給対象になりません。しかし、退職した場合でも、例外として以下の条件を2つとも満たせば出産手当金を受け取ることができます。
退職した場合でも受け取れる条件
- 退職時1年以上「継続」して健康保険に加入していた(健康保険任意継続の被保険者期間は除く)
(※)1日でも被保険者でなかった場合は認められない - 出産手当金の支給期間内(産前42日以前から産後56日後のうち休業期間中)に退職している
(※)退職日当日に出勤している場合は継続給付を受ける条件を満たさないため、資格喪失後の給付が認められない
\ お金・保険のことならマネードクターへ /
出産手当金の計算方法
出産手当金の支給額は、過去12ヶ月分の給料を基準(標準報酬)とした1日あたりの支給額×98日分です。1日当たりの受け取れる金額は以下の計算で算出されます。
支給開始日の以前12ヶ月間の各標準報酬月額を平均した額
-
(※)÷30日×(2/3)
(支給開始日とは、一番最初に出産手当金が支給された日のことです)
出典:「出産手当金について. 全国健康保険協会」
具体的にいくらもらえるか計算してみましょう。たとえば、12ヶ月間の各標準報酬月額が30万円で、出産前42日間、出産後56日間休んだ場合、計算式に当てはめると1日あたりの支給額は6,667円。すなわち、日額6,667円×支給対象期間98日分の653,366円が出産手当金の額になります。
(※)支給開始日の以前の期間が12ヶ月に満たない場合は、次のいずれか低い額を使用して計算します。
ア 支給開始日の属する月以前の継続した各月標準報酬月額の平均額
イ 標準報酬月額の平均額
・28万円:支給開始日が平成31年3月31日までの方
・30万円:支給開始日が平成31年4月1日以降の方
出産手当金の正確な給付額については、所属する健康保険組合の窓口にお問い合わせください。


出産手当金の申請方法
出産手当金を受給するには、出産する女性本人が加入している勤め先の健康保険組合や協会けんぽに申請をして、必要書類の提出を行わなければなりません。出産手当金を申請する際には、書類の記入や手続きに勤務先と出産した施設の医師などの協力が必要です。あらかじめ、勤務先から所定の申請書を受け取るなど、計画的に準備が必要になります。流れや手続き方法をしっかり確認し、必要時には勤務先や病院に相談しておきましょう。
また、出産手当金の申請期間は産休開始日翌日から2年以内です。この期間をすぎると、手当が徐々に減額されていくため、注意してください。
申請には、
申請に必要な4点の書類
- 健康保険証
- 母子手帳
- 印鑑
- 事業主の証明書類
上記4点の書類が必要です。
まず、会社に健康保険の加入状況を確認し、産休取得予定から出産手当金の受給取得資格があるかどうかを確認しておきます。次に、母子手帳のコピーなどを提出し、会社から「健康保険出産手当金支給申請書」を受け取り、必要事項を記入します。
医師・助産師が記入しなければならない事項もあるので、入院時など医療機関にいるタイミングで申請書を書いてもらいましょう。記入に時間のかかる病院もあるので、早めに相談・準備しておくといいでしょう。
出産後、健康保険出産手当金支給申請書を会社の担当部署へ提出し、事業主証明欄に記入してもらいます。申請から1〜2ヶ月の範囲で指定口座に一括で振り込まれます。
| 期間 | 順序と手続きの内容 |
| 産休前 | 1 自分が受給対象かどうか確認する 2 勤務先の健康保険担当窓口にて、「健康保険出産手当金支給申請書」(以下、申請書)を入手する(加入している健康保険のっホームページからもダウンロード可能) 3 申請書に必要事項を記入 |
| 産休中・出産入院時 | 4 申請書ない、「医師・助産師記入欄」を担当医師・助産師に記入してもらう(施設によって文書料がかかる場合もある) |
| 産休明け (産後56日経過後) |
5 勤務先の健康保険担当に提出(「事業主が証明するところ」を記入してもらう」 6 申請の1ヶ月〜2ヶ月後に指定した口座にに一括で振り込まれる |
申請期限は産休開始から2年間となっています。申請期限以内であれば全額支給を受けることが出来ます。2年を過ぎると1日毎に受給額が減少していくので注意が必要です。
予定日より早く出産すると損をする?
前述のとおり、出産手当金の支給期間は出産日を基準に、産前は42日間です。出産が出産予定日より遅れた場合、遅れた期間でも出産手当金が支給されます。では、出産予定日より早く出産した場合は、出産手当金はどうなるのでしょうか。出産日が早まった分、出産手当金が受け取れず損をしているように思えます。下記で詳しく解説します。
余裕を持って早めから産休を取得しておく
産休開始日ギリギリまで勤務していた場合、たとえ産休開始日が早まっても、その期間中「出産を理由に休んでいない」「勤務先から給料はもらっていた」ことになるので、出産手当金をもらう条件を満たしていません。そうなると、出産手当金はその日数分カットされてしまいます。予定分娩の場合など早めに産まれることがわかっている場合は、産休開始日より余裕を持って休みを取得しておくと安心です。
出産手当金の入金が遅い場合、早く欲しい場合の対処方法
出産後、赤ちゃんを迎え入れると、オムツや衣服など何かと育児や養育にお金がかかります。では、出産手当金の振り込みはいつになるのでしょうか。出産手当金の支給は手続きや処理に時間がかかるため、一般的に給付実施の振込日まで2〜4ヶ月かかると言われています。最短でも産後2か月半以上です。
例えば、6月1日に出産をして、6月30日に出産手当金の申請をしたとします。すると、9月末~10月末が出産手当金をもらえる目安となります。
このように支給日まで時間がかかるため、妊婦さんにとってはそれまでの生活費が心配になります。
以下で、出産手当金の遅くなる理由や少しでも早くもらえる方法について紹介します。是非、参考にしてください。
出産手当金の入金が遅くなるのは何の要因?
出産手当金の入金時期が遅い理由は、まず、申請書に産休期間を書き込まなければいけないためです。つまり、出産手当金を産前・産後分まとめて申請する場合、産後休暇の56日経った後に申請するため、その分出産手当金の入金が遅くなります。また、医師や助産師による記入事項もあり、退院後に再度産院へ足を運んだり、用紙を郵送したりすると余計に手間と時間を要します。
次に、出産手当金は給与が支払われなかったことを確認しなければならないため、申請書は会社経由にて加入先の健康保険組合に提出しなければなりません。会社によっては申請後の処理締め日が決まっている場合や、多くの申請書をまとめて処理していることもあります。
そのため、すぐに申請書が健康保険組合へ提出されるわけではありません。また、提出しても出産手当金の申請書に記載誤りや押印忘れなど、不備があった場合は申請書の差し戻しや再申請が必要です。
このようにさまざまな理由により、支給申請から審査が完了するまでは出産手当金が支給されないため、振り込み日が遅くなります。
出産手当金を早くもらうための方法
なるべく早く出産手当金の支給を受けるためにどうすればいいでしょうか。以下で解説します。
①産前・産後などで、可能なら分けて申請する
「出産手当金は産後56日を過ぎて一括で申請するもの」と思っている方も多いのではないでしょうか。実は、産前分と産後分を複数回に分けて申請、支給してもらうことが可能です。合わせて申請した場合に比べ、支給までの期間を短くできます。
例えば、医師の記入欄については産前分で申請済みの場合、産前後では省略できます。ただし、事業主の記入欄については逐一記入してもらうことが必要です。
②会社の担当者に事前に確認・相談しておく
前述のとおり、出産手当金の申請は会社経由にて提出されるため、あらかじめ担当者に事情を説明し、会社に早く処理してもらえるよう相談してみましょう。
③申請書類を産前から準備しておく
申請書を出産後に用意しはじめたのでは、手元に届くまでに時間がかかります。申請書類は産前産後に関わらず入手することが可能なので、早めに準備し、事前に記入できるところは埋めておきましょう。
④入院中に医師・看護師に書類の記入をお願いしておく
出産後、産院の医師や助産師に出産証明をもらわなくてはいけません。そのため、退院時にもらうことができるよう依頼しておくと、何度も病院に行かなくて済みます。とくに里帰り出産の場合は、里帰りが終了してから医師や助産師に記入してもらうこともあります。事前にお願いしておけば、実家に戻る時間や、書類郵送のやり取りをする無駄な時間のロスを防ぐことができます。
まとめ
出産手当金は産休中の生活の応援になる、とてもありがたい制度です。しかし、手続き方法や仕組みなどは人によっては複雑に感じられるかもしれません。そのため、事前に出産手当金を受給するための申請方法や金額、期間、その他注意点についてよく理解しておくことが重要です。出産後は心身ともに疲労し、申請が億劫になる場合が多いため、産休中の少し余裕がある期間に、ゆとりをもったスケジュールで準備するようにしましょう。加えて、情報を調べてもわからないなどの場合は是非FPなどにも相談や質問してみましょう。
\ お金・保険のことならマネードクターへ /
よくある質問
| Q | 出産手当金の申請に期限はありますか? |
| A | |
| Q | 退職後でも出産手当金を申請できますか? |
| A | 以下の3つの条件を満たしていれば、退職後でも出産手当金をもらうことができます。
下記の記事で、「退職後にもらえないケース」と合わせてさらに詳しく解説しています。 |
| Q | 出産手当金を産前・産後に分けて申請することはできますか? |
| A | はい、可能です。ただし、事業主の証明が申請するたびに必要になるため、まとめて申請することをおすすめします。 |