
米国株の投資先を検討するときには、配当利回りに着目するのが一つの考え方といえます。もしくは、新興企業に投資して急成長に伴う高収益獲得を狙うのも一つの方法です。米国株には配当回数が多いことや、取引銘柄が豊富であるなどのメリットがあります。一方で、情報収集がしづらいことや為替リスクがあるなどのデメリットには留意しましょう。本記事では、配当利回りが高い米国株をランキング形式で紹介します。銘柄比較の参考にしてください。
米国株の配当利回りが高い銘柄ランキングTOP5
9月28日時点で配当利回りが高い米国株上位5銘柄のランキングは次の通りです。| 順位 | 銘柄 | 配当利回り |
| 1位 | エクイティ・コモンウェルス(EQC) | 22.97% |
| 2位 | メディカル・プロパティーズ・トラスト(MPW) | 21.62% |
| 3位 | TORMA(TRMD) | 20.17% |
| 4位 | グローバル・ネット・リース(GNL) | 16.43% |
| 5位 | AGNCインベストメント(AGNC) | 15.23% |
参考:米国株 予想配当利回りランキング(高配当利回り順) - 日本経済新聞 (nikkei.com)(2023年9月28日6:46時点)
ランキング上位に掲載されている銘柄は、いずれも10%以上の配当利回りがあり、1年で魅力的な配当収入が期待できます。続いてトップ5の銘柄の詳細データをご紹介します。
1位:エクイティ・コモンウェルス(EQC)
エクイティ・コモンウェルス (NYSE: EQC) は、米国における不動産投資信託(REIT)の一角です。米REITは日本のJ-REITと異なり、自社で不動産開発を手がけることもできます。不動産やファンド運営に関する業務も、自社で運用するREITが多くみられます。
税法上の優遇を受けるものの、事業内容としてはより日本の不動産会社に近いイメージです。 同社は、シカゴに拠点を置くREITで特に米国の商業オフィス不動産を保有しています。「内部管理型」と呼ばれる自社で従業員を雇用して不動産運営を行うタイプのREITで、不動産経営による収入獲得や資産価値の向上を目指しています。
今期2023年に売上高が悪化する見込みであることもあり株価が低下していますが、2023年10月時点では2023年、2024年とも黒字は維持できる見通しです。
2位:メディカル・プロパティーズ・トラスト(MPW)
メディカル・プロパティーズ・トラスト(MPW)も、米国のREITの一種で、こちらも内部管理型の不動産投資信託となっています。同社はヘルスケア施設の運営を主としています。
ポテンシャルのある施設を買収し、長期のネットリース(税金を賃借人が負担する賃貸借契約)という形式で医療機関事業者に貸し付けて、賃料収入を獲得するビジネスモデルです。内部管理型なので、自社で施設の運営・管理を行います。
株価が少なくとも過去10年来の最安値付近で推移しており、その分PBRが低水準です。株価の下落が配当利回りの高騰の背景にあります。ただし、業績予想においては2023年~2024年とも黒字を維持する見通しです。見通し通り業績が上向くようならば、現在は割安な水準といえるでしょう。
3位:TORMA(TRMD)
TORMA(TRMD)は本拠地がイギリスの企業ですが、米NASDAQに上場しています。いわゆる海運業の一角で、ガソリン、ジェット燃料、ナフサ、ディーゼル油など石油製品の輸送を手がけています。
グローバルに大手石油会社や貿易会社との輸送取引を手がけていて、デンマーク、フィリピン、インド、シンガポール、米国などグローバルに拠点をもつ企業です。 2021年12月期には赤字計上するなど不調な時期もありましたが、2022年12月には急回復しました。
同期時点でROA21.52、ROE44.02など、資本効率の良い経営状況となっています。前期には及ばないものの、2023年12月も引き続き売上は高水準を維持する見通しです。景気循環との連動が大きいセクターでありながら業績見通しが安定している点は、この銘柄に投資する上ではサポート材料となります。
4位:グローバル・ネット・リース(GNL)
グローバル・ネット・リース(GNL)は不動産投資信託で、米国、西ヨーロッパ、北ヨーロッパ全域で事業を営んでいます。商業施設のネットリース形式でのテナント事業を主体としています。シングルテナントで収益を生む物件を中心に投資しているのが特徴です。
なお、モーゲージローン、メザニンローン、優先株式、または証券化ローンの組成なども行っています。 米国に限らずグローバルに51業種、138のテナントの賃貸運営をしていて、約56%が産業・流通物件、41%がオフィス物件、3%が小売物件です。
米国の底堅い景気やインフレも背景に、今後業績は上向く見通しで、2023年12月期、2024年12月期と売上高が拡大する見通しです。過去5年でみると、株価が下落傾向にあるため配当利回りも高止まりしています。しかし、見通し通り業績が上向けば、株価が反転し始める可能性もあるでしょう。
5位:AGNCインベストメント(AGNC)
AGNCインベストメント(AGNC)も、米国の不動産投資信託の一角です。ただし、同社はエージェンシー住宅モーゲージ担保証券(エージェンシーRMBS)に借入を活用してレバレッジをかけながら投資するのが特徴です。
このRMBSは一般消費者の住宅ローンを裏付けとして発行される債券で、元利金の支払いについて政府支援機関または米国政府機関の保証が付与されているのが特徴です。現物の不動産に投資するよりも低リスクなのが特徴です。
RMBSの流通が促進するほど、金融機関のローン組成が促進され、消費者は住宅ローンを活用して住宅保有をしやすくなります。AGNCインベストメント(AGNC)は間接的に米国の住宅市場の安定・発展に貢献している企業といえます。
2022年12月期に赤字計上するなど業績悪化もあり、株価は下落傾向が続いています。ただし、2023年12月は業績が回復して、黒字回復する見通しです。今後の動向に注目したい銘柄です。
米国株の配当の特徴
米国株は、日本株と比べて配当利回りが高いのが特徴です。また、配当回数が年4回と日本より多いことも魅力の一つといえます。「ジョンソン&ジョンソン」や「コカ・コーラ」のように長期にわたり増配を続けている企業も複数みられます。全体として日本企業と比較して配当による株主還元を重視しているのが特徴です。
高配当株が多い
日本と比較すると配当をしっかりと出す株や高配当株が多いのが特徴です。株によって株価の水準が異なるため、単純に配当額をみても配当の魅力の高さは判断できません。株価の違いを平準化して公平に判断するためには、年間配当額を株価で割った配当利回りでみる必要があります。
米国株は、下図の通り配当利回りが2.5%以上の株が全体の約50%を占めます。また、無配当の株が14%程しかないのも特徴です。
米国株では、株主優待を出すのがあまり一般的ではなく、自社株買いや配当などを通じて株主還元を行います。株主優待にコストを割く必要がない分、配当に資金を充当しやすいため、配当利回りが高い傾向にあるのです。
配当の回数が多い
米国株は、基本的に年4回の配当を付与する企業が多くなっています。日本では、配当が出るとしても年1~2回の企業がほとんどなので、米国株の方が頻繁に現金を受け取れるのが特徴です。継続的な配当収入を期待して株式投資をする方にも、米国株は適した投資先といえます。
なお、配当回数が多いからと言って配当利回りが高い、配当総額が多いとは限らない点には注意しましょう。配当利回りは年間の配当額合計を株価で割るため、配当回数が多くても配当利回りの上昇要因とはなりません。
連続増配銘柄が多い
米国株には連続して増配する企業が複数みられます。有名なところでは「ジョンソン&ジョンソン」や「コカ・コーラ」で、いずれも半世紀以上にわたって増配を継続しています。株式市場全体の成長や経済成長を土台として、配当収入の増加が期待できます。
配当が着々と積み上げれば、長期投資するほど配当込みのトータルリターンでみたときの損失リスクを抑制可能です。継続的に増配する株であれば、持ち続けている内に年間配当額が増えていき、さらに潤沢な配当収入が期待できます。
\ 楽天証券の口座開設はこちら /
米国株のメリット
米国株投資は、日本と比べて上場企業が多いのが特徴です。1株から投資できるため、少額から始められるのも魅力といえます。
配当利回りが高いため、投資元本に対して配当を多く受け取れます。過去のGAFAMのように急速に成長して価格上昇する企業が多いのも特徴です。
上場企業数が多い
米国の主要な株式市場であるニューヨーク証券取引所とNASDAQの上場企業を合計するとおよそ5,900社にのぼります。日本の上場企業数はおよそ3,900社なので、日本より上場企業数が多いのが特徴です。米国株は、日本株よりも投資の選択肢が豊富といえます。
米国内の銘柄には、多くの代表的な企業があり、それらは世界の時価総額ランキングや投資ランキングでも常にトップです。
さまざまな業種やリスクの企業が上場しているため、自分のスタンスやリスク許容度に合わせて自分にあった銘柄へ投資できます。また、銘柄が豊富であれば、分散投資がしやすいのも魅力です。
さらに、米国株の市場の時価総額は日本のおよそ8倍です。世界一巨大な市場であるだけに、取引参加者が多く流動性も高いといえます。市場環境が変化する中でも、売買を正常に成立させられる可能性が高いと期待できます。
少額から投資できる
米国株は基本的に1株単位で投資ができる市場となっています。そのため、株価に手数料を足した金額がそのまま投資金額となるため、わかりやすいのが魅力です。また、日本では基本的な株価の投資単位が1単元=100株なので、多くの銘柄で数万円~数百万円と多額の投資資金が必要になります。
単元未満で投資できるサービスを提供している証券会社も一部あるものの、寄付きや引けの成行でしか売買できないなど制約があるケースが多いです。
米国株は、そもそも市場のルールとして1株単位で売買できるので、数万円もあれば多くの銘柄が売買できます。初心者が少額から始められるため、チャレンジしやすい資産といえます。
配当金を多くもらえる
配当利回りが平均的に高く、配当を多くもらいやすいのが特徴です。日本よりも米国は株主を重視する姿勢が強く、本業に使わない余剰資金はできるだけ株主に還元する姿勢が強いといえます。
配当を積極的に還元するほか、自社株買いなども前向きに行います。先に紹介したとおり配当の支給回数が年4回と多いため、頻繁に現金収入が獲得できるのも特徴です。
成長力のある新興企業が多い
日本と比べて、新興企業が急成長して大手企業に化けるケースが多く見られます。近年で言えばGAFAMは、過去10~20年のうちに新興企業から一気に世界有数の大手となった企業群です。電気自動車のテスラも、近年急速に株価が上昇しました。
経済成長率が高く、またスタートアップを積極的に支援する風潮が日本よりも強いため、高成長を遂げる株が多くみられます。うまく銘柄を選べば急速に資産を拡大させるチャンスがあるのも、米国株の魅力です。
米国株のデメリット
日本人が米国株に投資する場合、投資企業の情報収集がしづらいのが難点です。米国株は米ドルで発行されている資産なので、ドル円の為替リスクがある点もデメリットといえます。
この為替に対する手数料が取引手数料に加えてかかるため、手数料が割高になりがちな点も気になるところです。最後に、米国時間に市場が開くため、取引時間が夜中~未明になる点も日本人にとっては米国株に投資するデメリットといえるでしょう。
企業の情報を集めにくい
米国企業の財務情報や、事業内容が詳しく書かれた資料は英文になるため、情報収集が難しいのがデメリットです。日本で知られたグローバル企業ですら、業績や財務情報を詳しく調べるとなると英文を読み込まなければなりません。
現代では翻訳サイトなども豊富にあるとはいえ、英語が苦手な方にとってはハードルが高いと感じるでしょう。 しかし、楽天証券やSBI証券など大手のネット証券の中には外国株でも豊富な情報を提供している場合もあります。
また、ロイターなど一部のグローバルな情報ベンダーは海外企業の情報も日本語に翻訳しています。こうした情報ソースも活用しながら、米国マーケットや米国株の銘柄についてうまく情報収集してください。
為替リスクがある
米国株は米ドル建てで発行されている資産であるため、為替リスクが発生するのがデメリットです。証券取引所では米ドルで取引されているため、日本人は購入時に日本円を米ドルに変換する必要があります。
為替手続き自体は、ネット証券会社であれば株の購入時に一緒に手続きできるため、大きな手間はかかりません。 しかし、購入時と売却時の為替変動によって損益が変化するリスクがあります。
購入時から売却時にかけて円安になれば、収益の拡大要因となるのでいいですが、円高になった場合は、現地の株価が上昇しているのに損失が発生するリスクがあるのです。
また、配当金についても円建ての金額はその時々の為替水準によって変化することになります。
取引手数料が割高
多くの証券会社では米国株を日本円から取引する場合、株の取引手数料とドル円の為替手数料が二重にかかります。そのため、日本株を売買するよりもしばしば割高になりがちです。
日本株については、楽天証券やSBI証券で売買手数料が無料化されたため、二重の手数料がかかる米国株はさらに割高に感じられます。株価は上昇しているのに、手数料を取られて損失になる「手数料負け」の状態にならないように留意しながら売買タイミングを考えて行かなければなりません。
ネット証券は全般的に米国株関連の手数料が低い傾向にあります。なかでもマネックス証券は買付時の為替手数料が無料ですし、DMM証券は米国株の取引手数料がかかりません。このように手数料の低い証券会社をうまく利用して、手数料が割高な米国株においても投資コストを抑えるのが有効です。
取引時間が夜間
米国市場での取引時間は9:30~16:00で、日本時間にすると23:30~翌6:00(サマータイムは22:30~翌5:00)です。日本の夜間から取引が始まり、深夜~未明にかけて市場が動くため、多くの方にとっては米国株市場をリアルタイムでチェックするのは困難です。
寝てる間に市場が動くリスクを受け入れながら、起きている時間に売買するしかありません。 ただし、東証の取引時間は9:00~15:00で、多くの社会人が業務時間中にあたるため、意外に売買しづらい方も少なくありません。22時~23時台に市場が開く米国市場の方が、むしろ取引しやすいと考える人もいます。
\ 楽天証券の口座開設はこちら /
まとめ:米国株に投資して配当金を多く受け取ろう!
米国株は、潤沢な配当や高い成長性、1株単位で投資できるハードルの低さなどが魅力です。配当利回り上位の銘柄になると、20%近い高利回りなど日本株と比べて際だって高水準となっています。
また、アメリカには半世紀以上もの間増配が続く優良企業や、10年~20年で10倍も株価成長を遂げる企業など、上場企業数が多く投資の選択肢が豊富なのもメリットといえます。 配当を積み上げ長期投資したい人にも、急成長を捉えて高成長を狙いたい人にも、米国株はおすすめです。
情報収集がしづらい、為替リスクがある、取引時間が夜間になるなどのデメリットもあるものの、米国株は有力な投資の選択肢の一つといえるでしょう。
これから配当水準に着目して米国株投資を始めようと考えている方は、ぜひ今回の配当利回りランキングを参考にして、ご自身の目的に合った投資銘柄を選んでください。
\ 楽天証券の口座開設はこちら /



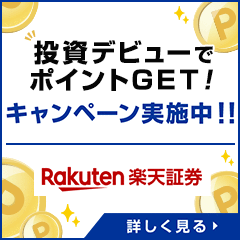

%20(1).png)

-min.png)








